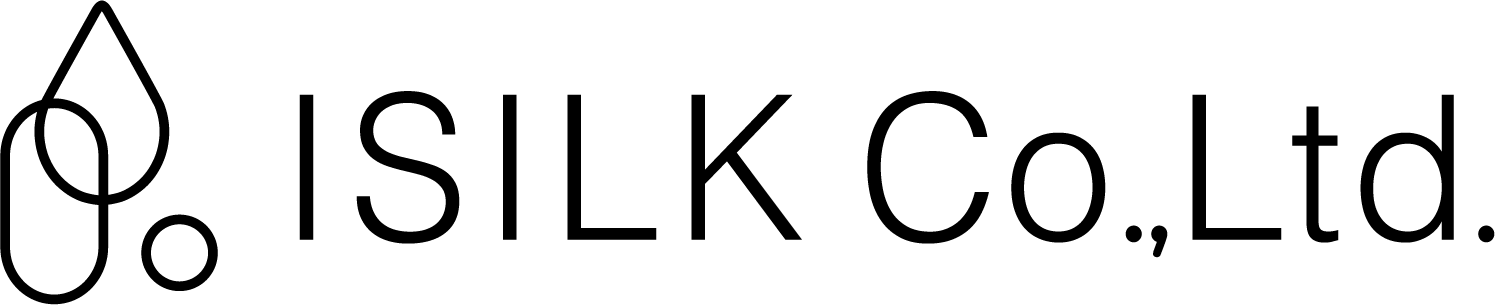渋沢栄一とは何をした人? ― 秩父鉄道とセメント産業を支えた「日本資本主義の父」
2024年、新一万円札の顔が福沢諭吉から渋沢栄一へと変わりました。キャッシュレス時代のいま、現金に触れる機会は減ったものの、紙幣の肖像が変わるという出来事は日本中で注目を集めました。
けれど、こう思った方も少なくないかもしれません。
「渋沢栄一って、結局何をした人なの?」
この記事では、渋沢栄一の思想と功績を概観しながら、とくに秩父鉄道や秩父セメントとの関わりに焦点を当て、現代に受け継がれる地域とのつながりについてご紹介します。

渋沢栄一とは ― 500以上の企業を支えた経済人
渋沢栄一(1840–1931)は、埼玉県深谷市(旧・武蔵国血洗島)出身の実業家で、「日本資本主義の父」と称されています。
官僚として明治政府に仕えた後、実業界へ転身。以後、500以上の企業・団体の設立・運営に関与し、近代日本の経済基盤を構築しました。
主な支援・設立企業には次のようなものがあります:
-
第一国立銀行(現:みずほ銀行)
-
東京証券取引所
-
帝国ホテル
-
サッポロビール
-
東京ガス
-
王子製紙
-
日本郵船 など
これらの企業は現在も、日本の産業や暮らしを支える重要なインフラとなっています。
渋沢栄一の思想:「道徳経済合一」とは?
渋沢の信条は、「道徳と経済は両立すべきである」という理念、すなわち「道徳経済合一」です。
ただ利益を追求するのではなく、倫理的で持続可能な経済活動を目指すという考え方は、現代のCSR(企業の社会的責任)やSDGsにも通じるものです。
秩父との関わり ― 秩父鉄道とセメント事業の発展を支援
■ 秩父鉄道:地域と資源をつなぐ交通インフラ
1899年に開業した秩父鉄道(旧・上武鉄道)は、熊谷と秩父を結ぶ重要な鉄道であり、秩父地域の産業・観光発展の基盤となる存在です。
この鉄道の発起人である柿原萬蔵(秩父の養蚕業者)の志を継いだ柿原定吉とともに、渋沢栄一は資金調達・人脈形成を支援。
また、自身の縁戚である本庄の実業家・諸井恒平(秩父セメント創業者)や、小鹿野町出身の山中隣之助(浪速銀行頭取)などとも連携し、鉄道と資源開発を連動させる仕組みを構築しました。
結果、秩父鉄道は単なる交通網にとどまらず、石灰資源の輸送・経済循環の軸として、地域全体の近代化に貢献しました。

秩父セメント:近代建築を支えた地域資源
秩父の石灰岩を活かして1898年に設立された秩父セメント(現:太平洋セメント)もまた、渋沢の支援を受けて成長した企業です。
渋沢は技術導入・経営体制の整備を後押しし、秩父の自然資源を都市のインフラ整備の原料へと転化しました。東京の都市化を支えた多くのコンクリート構造物に、秩父産のセメントが使われているのです。

現代につながる渋沢の精神と、私たちの挑戦
渋沢栄一が重んじた「地域資源を活かす産業育成」と「倫理ある経済活動」という2つの柱は、現代の私たちにも多くの示唆を与えてくれます。
秩父を拠点とする私たちISILKでは、地域の自然素材——たとえばクロモジ精油など——を活用し、「香りというかたちで秩父の恵みを現代に届ける」という挑戦を続けています。
BLACKLETTERS ― 秩父の自然資源を、香りとして再構築する
ISILKが展開するフレグランスブランド「BLACKLETTERS」では、秩父のクロモジなどを活かした天然精油をもとに、空間や気持ちを整える香りを提案しています。
渋沢がかつて「セメント」と「鉄道」で地域をつないだように、私たちは「香り」で人と自然、都市と地方をつなぐ——そんな現代版の“地域資源再生”を目指しています。
まとめ ― 「人と地域を動かす力」は今も生きている
渋沢栄一は、日本の経済基盤を築いただけでなく、秩父地域においても鉄道・セメントという重要産業の発展を支えました。
彼が掲げた「道徳と経済の両立」という精神は、時代を超えてなお有効であり、地方創生やサステナビリティが求められる今こそ、再び注目されるべき思想です。
私たちISILKもまた、秩父の自然資源を現代の文脈で再構築し、未来につながる価値へと育てていきたいと考えています。