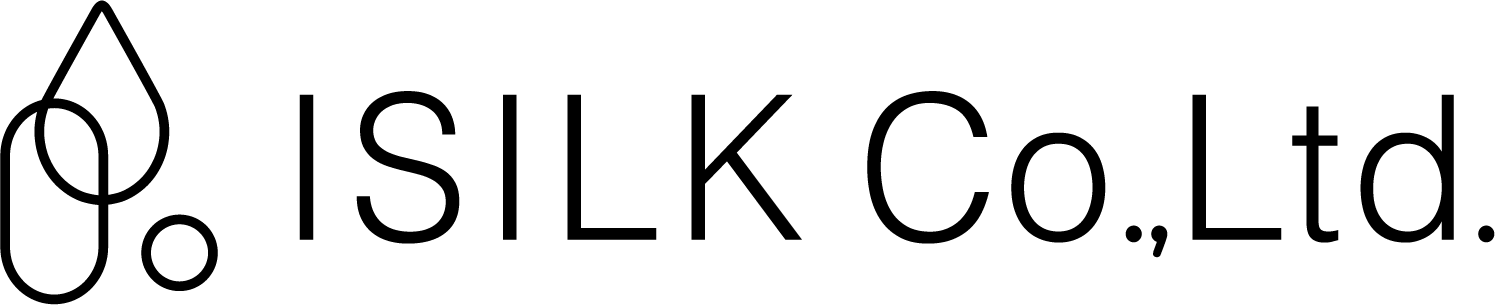削られた山と走る列車──武甲山と秩父鉄道が語る産業遺産の記憶
秩父を支えた「山と鉄路」の物語
秩父の風景を象徴する存在──武甲山(ぶこうさん)と秩父鉄道。山肌が大きく削られたその姿と、ゆっくり走る貨物列車は、長きにわたり地域の産業と暮らしを支えてきました。
本記事では、武甲山と秩父鉄道が果たした役割を軸に、秩父の産業遺産としての価値と未来へのヒントをひもときます。

武甲山とは|秩父のシンボルと石灰岩の山
標高1304mの武甲山は、秩父の象徴的な存在です。山の北側斜面には日本屈指の石灰岩鉱床が広がり、古くから漆喰やセメントの原料として採掘されてきました。
大正・昭和期には採掘量が一気に増加し、特に1940年代以降、セメント産業の発展とともに山体の姿は大きく変わりました。現在も、午後2時になると爆破音が秩父の谷間に響きわたり、採掘の現場が今も息づいていることを物語っています。
セメント産業と秩父経済を動かした巨人たち
石灰岩の商業利用を推進したのは、日本資本主義の父・渋沢栄一の縁戚にあたる実業家・諸井恒平でした。
彼が創業した秩父セメント(現:太平洋セメント)は、地域の雇用と経済を支える柱となり、秩父市内では「誰かがセメント工場で働いていた」ことが日常の一部として語られてきました。

秩父鉄道と貨物列車|石灰岩を運ぶ命綱
武甲山から採掘された石灰岩を運ぶために敷設されたのが秩父鉄道。
この鉄道は、観光客を運ぶ列車と貨物列車が同じ線路を行き交う全国でも珍しい運用形態を取り、セメント工場と消費地をつなぐライフラインとして現在も重要な役割を担っています。
貨物列車が通過する際の轟音や、長く閉じたままの遮断機の下で列車を見上げる子どもたちの姿──それは、秩父における産業と暮らしの風景でした。

武甲山と化石|かつて海だった秩父の地層
なぜ武甲山には石灰岩が豊富にあるのか──その答えは地質学にあります。秩父一帯はかつて海の底にあり、長い時間をかけて堆積した貝やサンゴ、プランクトンの殻が石灰岩となりました。
その証拠に、秩父の河川敷や山中では今でも貝殻の化石やサメの歯などが発見されており、学校の自然学習にも活用されています。
武甲山にまつわる伝説と秩父夜祭
武甲山は地元の信仰の対象でもあります。特に秩父神社との間には「年に一度の再会」を象徴するような伝説が残されており、12月3日の秩父夜祭では神と神が出会う神聖な日とされています。
この祭りは、かつて絹織物業で栄えた秩父の商人文化の象徴でもあり、ユネスコ無形文化遺産にも登録されました。
自然資源の再発見|秩父の香りを世界へ
セメントだけではありません。秩父の森にはもうひとつの“宝”があります。それが、和精油の原料として注目されている「クロモジ(黒文字)」です。
この香木の枝葉から抽出される精油は、スパイシーさと柑橘系の爽やかさを併せ持ち、リラックス効果にも優れています。
BLACKLETTERS|香りで地域の記憶を届ける
「BLACKLETTERS」は、秩父産クロモジ精油を中心に、日本の風土や文化を香りで再構成するフレグランスブランドです。
-
KUROMOJI:無色透明な香りで、自分の“中心”と向き合いたいときに
-
URAHA:草木の裏側のような静かな生命力を感じる香り
-
SORAIRO:晴れた空のような、清々しい集中力を誘う香り
これらの香りは、秩父の自然・産業・歴史の断片を織り込み、「香りで記憶を運ぶ」ことを目指しています。
まとめ|山と鉄路、そして香りがつなぐ秩父の物語
削られた武甲山と、今も走る貨物列車。 その風景には、失われたものと、今も残るもの──そして未来へつなぐべき価値が詰まっています。
秩父の自然資源や文化を香りとして再解釈する「BLACKLETTERS」や「SHELOOK」のようなブランドが、その新たな地域価値の一翼を担いつつあります。
秩父の香り、秩父の物語。 あなたの暮らしにも、その余韻を届けてみませんか?