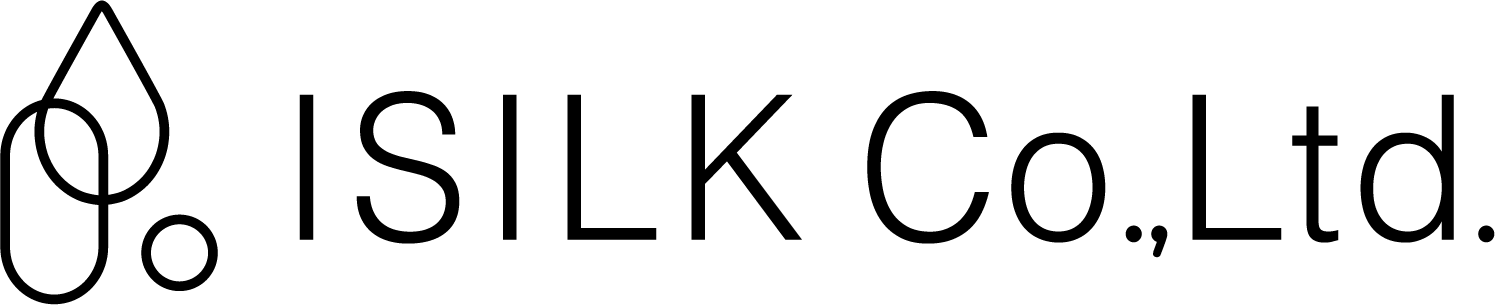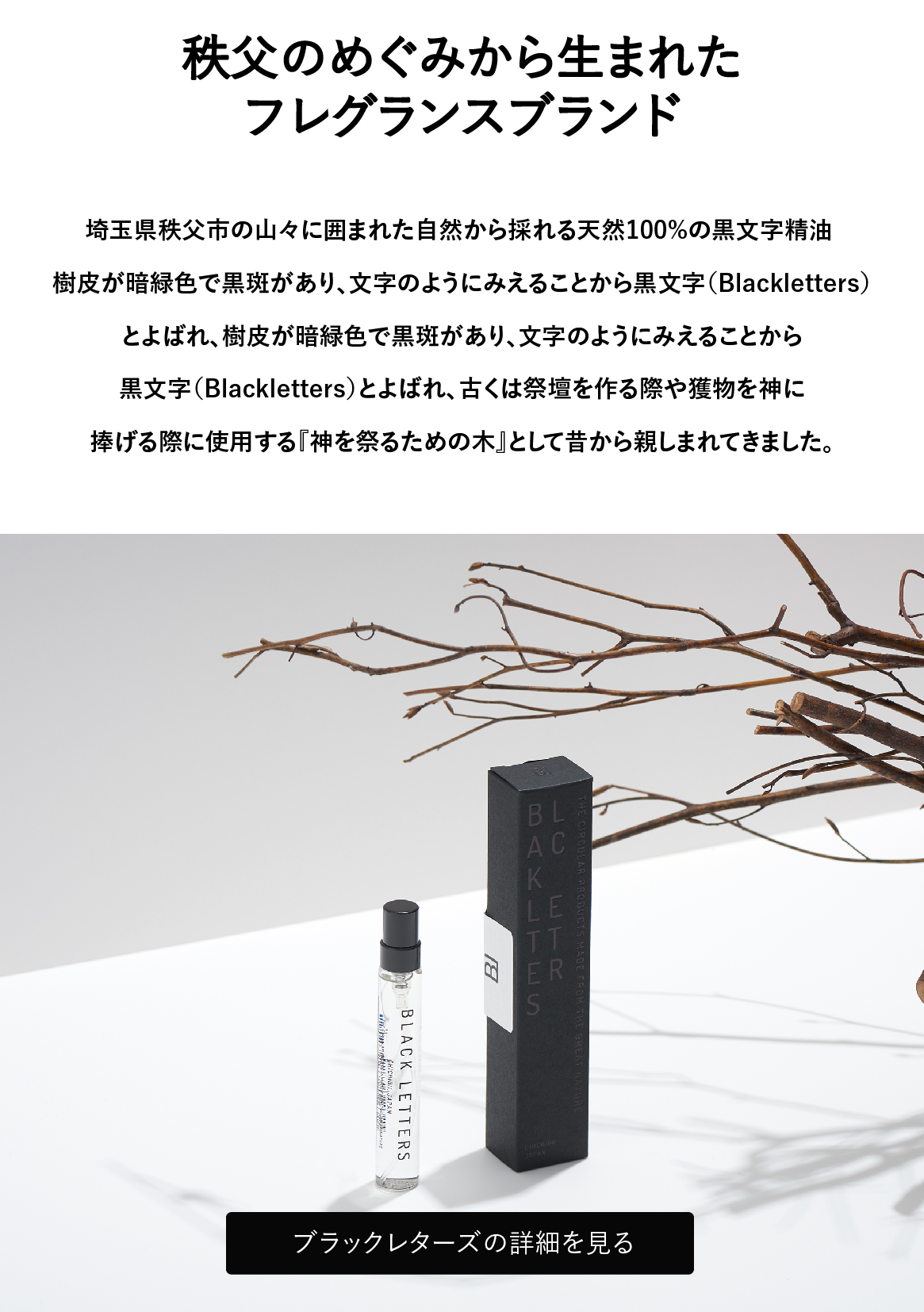日本で香水が売れない理由|文化・市場・嗜好の3視点で徹底解説
「なぜ日本では香水があまり売れないのか?」
海外、特にフランスでは生活に根付いている香水文化ですが、日本ではまだまだ日常使いには浸透していません。
本記事では、日本の文化的背景、市場動向、消費者嗜好の変化という視点から、日本における香水市場の現状と未来をわかりやすく解説します。

日本の香水市場の現状
日本の香水市場は、欧米や他のアジア諸国と比べても規模が小さく、特に若年層の間で香水離れが進んでいます。
2022年時点で市場規模は392億円(前年比2.6%増)とわずかに成長しているものの、ルームフレグランス市場など他の香り関連市場に比べると依然小規模です。
「香りを日常に取り入れる」文化の定着に苦戦しているのが現状です。

日本の文化的背景と香りへの価値観
日本では、控えめで自然な美しさが重んじられる文化があります。
-
古代インドから伝来した香文化は、仏教とともに定着
-
平安時代には「薫物合わせ」など、香りを混ぜて楽しむ文化も発展
-
香りを「聞く」と表現する「香道」という伝統文化も存在
これらからわかる通り、日本では香りは控えめに、繊細に楽しむものとされてきました。
さらに、無臭文化(体臭が少ない)や毎日お風呂に入る習慣(水資源が豊か)といった生活習慣も、強い香りを必要としない背景になっています。

他国(特にフランス)との文化的違い
-
日本:香水は「ファッションの仕上げ」や「気分転換」の一部
-
フランス:香水は「生活の一部」かつ「マナー」
フランスでは小学生から香水を使い始め、体臭と香水を一緒に楽しむ文化があります。
一方日本では、香水は必須ではなく、個人の好みに委ねられています。
香水のマーケティング戦略の課題
日本市場においては、香水のマーケティング戦略が欧米市場と異なる必要があります。しかし、多くのブランドはこの点を見落としています。
日本における香水のマーケティング戦略の課題は、主に商品の性質と売り方の二つの側面に分けられます。
- 商品の性質: 日本市場においては、生産の安定性や原価率の低減を考えた結果、合成香料を多用し、強い香りを持つ製品が多く市場に出回っています。しかし、これらの強くて長く続く香りが日本の消費者の嗜好に合わなかった可能性が高いです。
- 販売方法: 従来の香水の販売方法は、ブランドロゴや広告頼りの自己選択型販売か、過度に丁寧なカウンセリング販売のどちらかでした。これに対し、より高度な知識を持つスタッフによるフレンドリーな接客や、セミセルフ方式(顧客がテスターを嗅ぎながら自分で製品を選べる方式)が日本市場に適していると考えられています。
より「試して楽しい」「気軽に選べる」体験設計が求められています。

消費者の嗜好変化と新しい兆し
近年、日本では
-
パーソナライズされた香り
-
個人の肌になじむ「スキンセント」志向 が高まっています。
例えば、オルビスの「HELENUS(ヘレナス)」では個々の肌に合わせた自然な香りを提案するボディオイルが発売されるなど、香りに対する新しいアプローチが進んでいます。
結論と今後の展望
日本の香水市場の成長には、
-
文化的背景に寄り添う
-
控えめで自然な香りを提案する
-
パーソナライズ・体験型のマーケティングを行う
ことが欠かせません。
【秩父発】自然な香りで、新しい香水体験を
たとえば、秩父産クロモジ精油をベースにした【BLACKLETTERS】では、
日本人の感性に寄り添った、自然な香りの香水を展開しています。
合成香料の強い香りではなく、ふとした瞬間に感じる自然の香り」を大切にしたい方へ。
\新しい香り体験をあなたに/