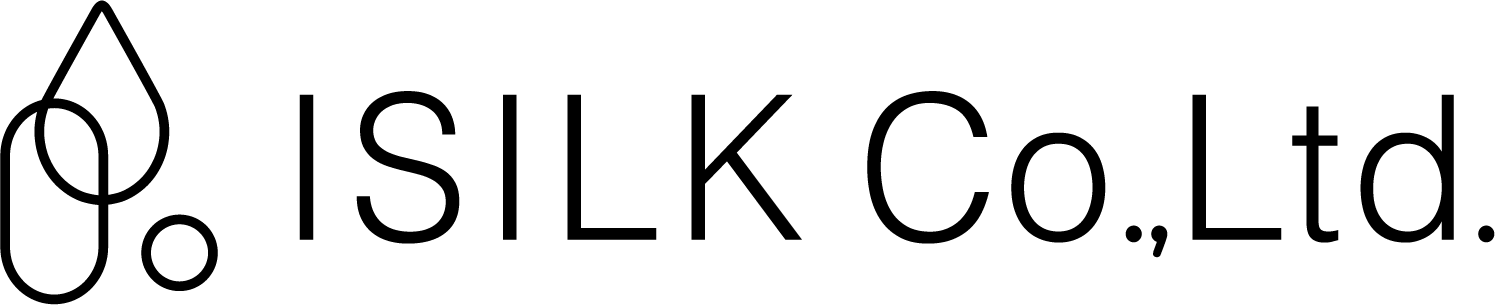国産シルクを活用した新たな挑戦:島精機製作所とホールガーメント
島精機製作所(Shima Seiki Mfg., Ltd.)は、和歌山県に本社を構える世界的なニット機械メーカーです。特に「ホールガーメント®(WHOLEGARMENT®)」技術は、縫い目のない立体的な服を一体成形で編み上げることで、ファッション業界に革新をもたらしました。
本記事では、島精機製作所の歴史や技術、そして国産シルクの一元化を軸にした新たな取り組みについて詳しく解説します。

島精機製作所の歴史と革新技術
創業と初期の歴史
島精機製作所は、1962年に島正博氏によって設立されました。最初は手動横編機の製造からスタートし、1967年には「SVS型」という手動横編機を開発。
この製品がニット業界での足がかりとなりました。当時、軍手の製造が主力で、立体的な編み上げ技術が革新をもたらしました。
コンピュータ横編機の開発
1978年、世界初のコンピュータ制御横編機「SDS型」を発表。これにより生産性が大幅に向上し、ニット製品の可能性が広がりました。
ホールガーメント®の登場
1995年、無縫製横編機「ホールガーメント®」が登場。生地、裁断、縫製という従来の工程を一体成形に短縮し、縫い目のないニット製品が可能に。
これにより、衣類生産の効率化と環境負荷の軽減が実現しました。
ホールガーメント®とは何か?
無縫製ニットの特長とメリット
ホールガーメント®は、編み上げ時に縫い目が発生しないため、フィット感や着心地が抜群です。また、生地の裁断が不要なため、素材の無駄を最小限に抑え、持続可能な生産方式として注目されています。
ホールガーメントミニの可能性
小型版の「ホールガーメントミニ」では、帽子、靴下、腹巻き、レギンスなど、多様な製品が編み上げられます。
特にシルク糸を活用すれば、より高付加価値な製品が実現可能です。現在、シングルジャカードやリブ編みの制約など課題はありますが、さらなる技術改善が期待されています。
国産シルク一元化の取り組み
国産シルクと海外産シルクの違い
現在、日本の養蚕農家で生産される国産シルクは、加工費の高さから価格が上昇傾向にあります。
一方で、中国やブラジルから輸入されるシルクは低コストですが、国内産との品質や加工法に違いがあります。
シルク製品の加工プロセス
- 繭の輸入:日本国内で繰糸、撚糸、精錬を実施。
- 絹糸の輸入:撚糸や精錬を国内で行うケースも。
- 絹紡糸の輸入:切り繭や綿状態で輸入され、日本で紡績されます。
このように、加工工程をどこで行うかが、製品品質やコストに大きな影響を与えます。

秩父から発信する新たな価値
地域活性化と観光誘致の可能性
秩父市では、歴史や神社仏閣と関連付けて地域の魅力を発信することも、日本三大曳祭りの1つでもある秩父夜祭は「絹のまつり」とも呼ばれていた背景も含め、国産シルクを使った製品を通じて、秩父の歴史や文化を世界にアピールすることで、観光客誘致にも貢献できるでしょう。
サステナブルな製品作りの展望
シルクの一元化により、養蚕農家の活性化や国内産業の振興が期待されます。さらに、ホールガーメント®技術を活用することで、環境に優しい製品づくりを実現し、国内外での競争力を高めることが可能です。
秩父から生まれた恵みを使用したフレグランスブランドBLACKLETTERS
秩父から生まれた恵みを使用したフレグランスブランドも秩父祭り会館でも取り扱いしていただいています。
香りもお試しできるので、ぜひスタッフにお声がけください。
詳細は下記をクリックしてもOKでこちらでもHP見れます。
次の記事へ