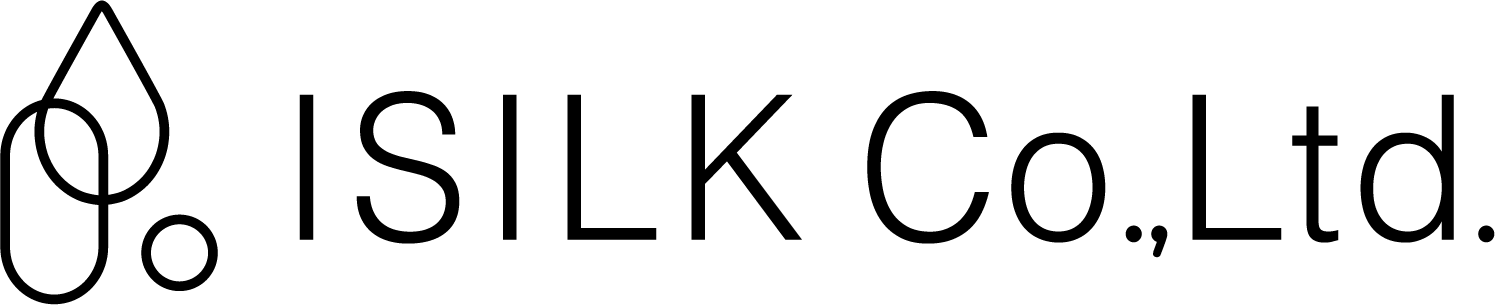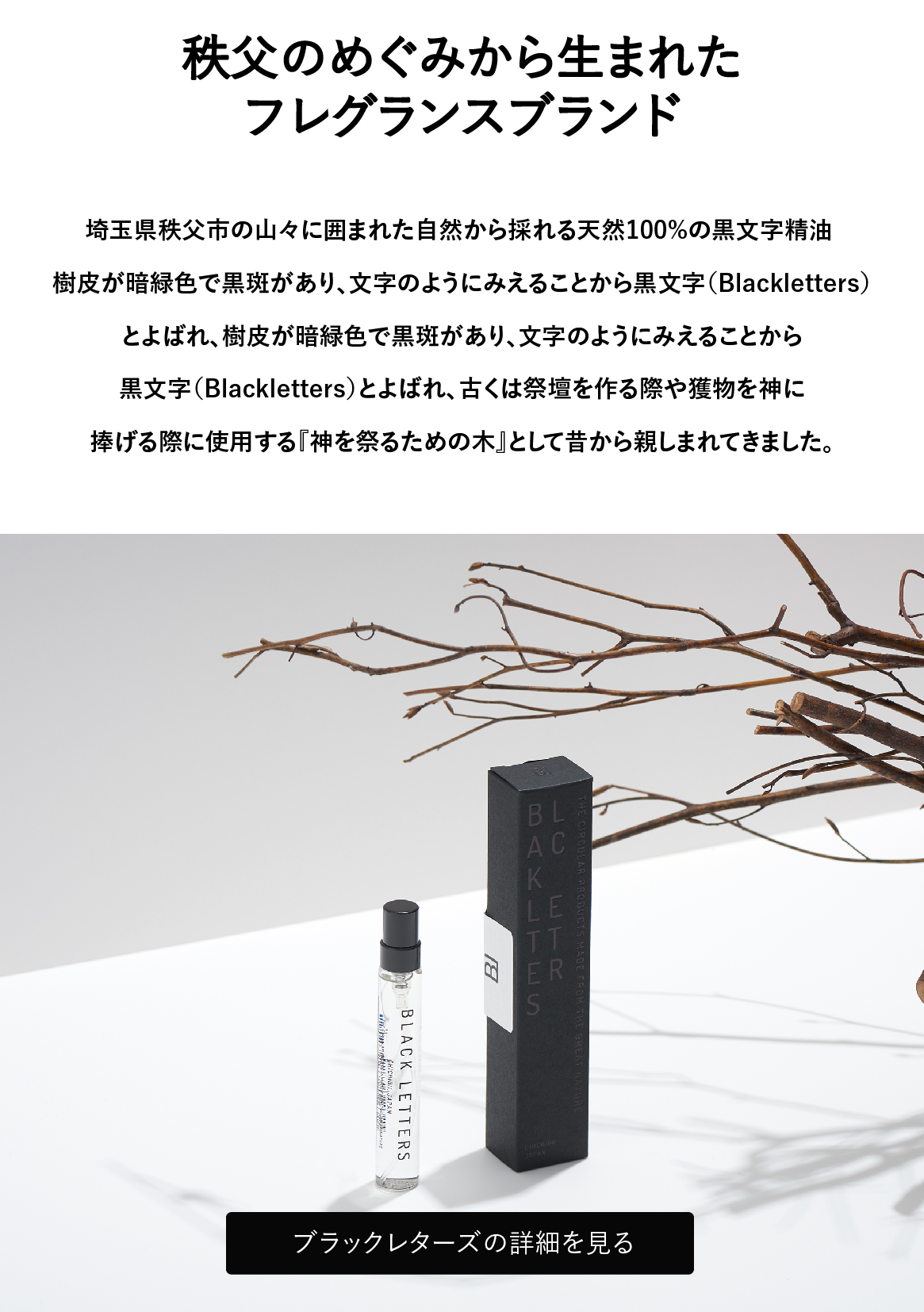なぜ蚕の繭は丸いのか?自然が生んだ構造美とシルクの秘密
― 繭のかたちに隠された、自然の知恵と人とのつながり ―
ふと手にしたシルク製品。その美しさや肌触りに心惹かれると同時に、原料である「繭」の形にも目を向けたことはありますか?なぜ、蚕の繭はあのように丸く、美しいかたちをしているのでしょうか。
この記事では、繭が“まるくなる理由”を、自然界のしくみ・蚕の行動・人との歴史的関わりの3つの視点から紐解きながら、秩父のシルク文化とブランドSHELOOK・BLACKLETTERSの取り組みまでをご紹介します。

Group of silkworm in white cocoon stage background
シルクとは?──蚕が生み出す唯一無二の天然繊維
シルクは、蚕(カイコ)が自身を守るために作る「繭」から得られる、動物性の天然繊維です。
その特徴は:
-
肌にやさしいアミノ酸構造
-
自然な光沢としなやかさ
-
人の髪の毛の1/5という細さ
肌に直接触れるスキンケア製品や高級寝具にも使われるほど、機能性と上質さを兼ね備えた素材です。

繭が丸い理由──蚕の「8の字運動」がつくる球体構造
蚕は、繭を作る際、頭を“8の字”に動かしながら糸を吐き出します。その回転運動によって、徐々に立体的で均等な球体に近い構造が出来上がるのです。
この構造には、驚くほど理にかなった利点があります:
-
保護機能:厚みと形状が外敵から身を守る
-
温湿度調整:内部の環境が安定しやすい
-
長い繊維:繭1つから約1,000mものフィラメントが得られる
つまり「丸い繭」は、自然が選び抜いた、蚕にとって最も機能的な“サバイバルのかたち”なのです。

家蚕と野蚕──人との関わりが生んだ繭の多様性
蚕は大きく分けて「野蚕」と「家蚕」に分類されます。日本で養蚕されているのは主に家蚕で、人の手によって品種改良されてきました。
-
日本種:くびれのある米俵型
-
中国・欧州種:くびれのない卵型・球形
繭の色にも違いがあり、白繭は染色がしやすく汎用性が高く、黄色や笹色の繭は自然な風合いを活かした無染色製品に活用されます。
現在、日本では500種以上の家蚕品種が保存されており、繭の形・色・大きさの多様性は、まさに人と自然の共同作品といえるでしょう。
秩父と蚕──養蚕の四季と土地の記憶
秩父地域はかつて、全国有数の養蚕地帯でした。
春〜秋にかけて、「春蚕」「夏蚕」「秋蚕」など、季節に応じて育てられ、繭が地域の産業と暮らしを支えてきました。
しかし現在、蚕を育てる農家は全国的にも激減。
秩父でもわずか数軒を残すのみとなり、知見と文化の継承が大きな課題となっています。

SHELOOKとBLACKLETTERS──繭の価値を未来につなぐ挑戦
SHELOOKでは、秩父の自然や風土に育まれた繭を活用し、シルクの魅力を最大限に引き出すアイテムを展開。
繭の背景にある物語に耳を傾けながら、スキンケアやライフスタイル商品へと昇華させています。
また、姉妹ブランドのBLACKLETTERSでは、繭の柔らかさや自然のニュアンスを香りで表現したフレグランスを展開。精油や自然由来の香料を使い、五感を刺激する世界観を築いています。
▶︎ BLACKLETTERSの香水を見る → 商品一覧はこちら
まとめ──「丸い繭」に宿る、自然と人の知恵
「なぜ繭は丸いのか?」それは、蚕の動き・自然のしくみ・人との関係性が重なり合った結果として、最も合理的かつ美しい形だったから。
そしてその形から生まれるシルクは、今もなお、私たちの暮らしにやさしさと豊かさを届けてくれます。秩父の繭文化を未来へつなぐために──
SHELOOKとBLACKLETTERSは、シルクに宿る「丸い想い」を、これからも丁寧に紡いでいきます。