精油は飲んでも大丈夫?知らないと危険な食品と医薬品の違い
アロマや自然療法が注目されるなか、「精油(エッセンシャルオイル)って飲めるの?」という疑問を持つ方が増えています。
特にSNSや輸入サイトでは「食品用精油」や「飲める精油」といった表現も見かけるようになり、混乱する人も少なくありません。
この記事では、精油が本当に“飲めるのか”という疑問を切り口に、食品と医薬品の法的な違いや、日本での精油の取り扱いについてわかりやすく解説します。

精油とは?自然の恵みが凝縮されたアロマ成分
精油とは、植物の花、葉、果実、樹皮などから抽出される天然の揮発性芳香成分です。香りを楽しむだけでなく、リラックス効果や集中力アップ、抗菌作用など、様々な機能が期待されています。
日本では主にアロマテラピーや香り雑貨の素材として使われていますが、海外では飲用や医療目的で使われることもあります。その背景には「食品」と「医薬品」の法律上の違いが関係しています。

「食品」と「医薬品」の違いとは?
この違いを理解するには、まず“食品”と“医薬品”の法的な定義を見てみましょう。
● 食品
-
日常的に摂取され、栄養補給や嗜好品として分類される
-
一般的に規制は緩く、製造時の品質管理も医薬品ほど厳密ではない
-
例:調味料、ハーブ、エッセンシャルオイルを少量添加したフレーバー商品 など
● 医薬品
-
疾病の治療・予防・診断、あるいは健康の維持・増進を目的に用いられる
-
製造・流通・販売すべてに厳格なルールと承認が必要
-
厚労省の承認を受けるまでに、臨床試験など長いプロセスを要する
つまり、同じ「精油」でも、使い方によって法律上の分類がまったく異なるのです。

日本における精油の立場
日本では、精油は基本的に「雑貨」として流通しています。つまり「飲んではいけないもの」として販売されています。
例え品質が高くても、食品としての検査や基準を満たしていない限り、口にすることはできません。
「飲める」と表記された海外製品を個人輸入した場合も、日本国内で「飲用」をすすめることは違法と見なされる場合があります。自己責任での使用も推奨されていません。
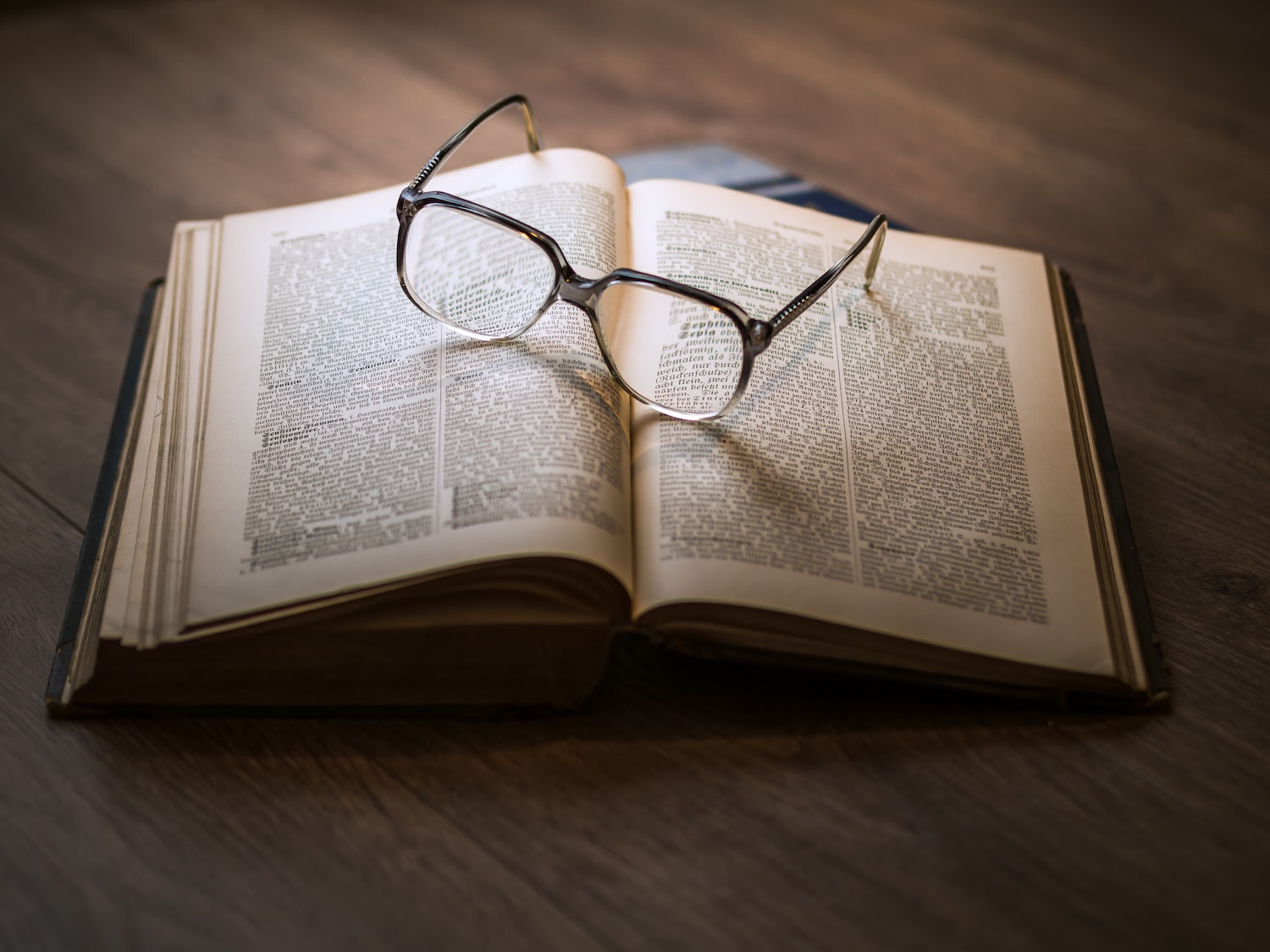
海外ではなぜ“飲める精油”があるのか?
例えば、アロマ先進国のフランスでは、医師や薬剤師の指導のもと、精油を医療行為の一環として使用する「メディカルアロマ」が一般的です。品質の保証と医療体制が整っているからこそ可能なのです。
しかし、日本ではそのような制度がないため、あくまでも香りを楽しむ雑貨としての取り扱いにとどまります。
精油の濃度と安全性:なぜ「飲む」にはリスクがあるのか?
精油は非常に高濃度です。1滴に数十枚の葉や花が凝縮されており、直接体内に取り入れると刺激が強すぎる場合があります。
たとえば、肌に直接塗布してかぶれを起こすこともあり、飲用すれば胃腸への負担やアレルギー反応などのリスクも。
日本ではこのような健康リスクを防ぐため、飲用は禁止されていると考えるとよいでしょう。
安全に香りを楽しむ方法とは?
精油の魅力を安全に楽しむ方法はたくさんあります。たとえば:
-
ディフューザーで香りを部屋に広げる
-
スプレーとして空間に使う
-
入浴剤に数滴加える
-
ハンカチやティッシュに垂らして持ち歩く
これらの方法なら、精油本来の香りとリラックス効果を手軽に取り入れられます。
BLACKLETTERSでも採用:香りの力を安全に生活に取り入れる
精油の力をもっと身近に、安全に楽しみたい方へ。私たちのブランド「BLACKLETTERS」では、秩父産の黒文字(クロモジ)をはじめとした国産精油を用いたフレグランスアイテムを展開しています。
自然由来の成分でありながら、香りの持続性と上品さを兼ね備えたプロダクトは、心地よい日常を支えてくれます。もちろん、飲用ではなく“香りを楽しむ”ための設計です。
▼ 黒文字精油をベースにしたアイテム一覧はこちら
まとめ:精油は「飲む」より「香る」が正解
精油は自然の恵みが凝縮された素晴らしい素材ですが、扱い方を間違えると体に害を及ぼす可能性もあります。特に日本では、法律的に飲用や医療目的での使用は認められておらず、安全に楽しむには正しい知識が欠かせません。
日常に香りを取り入れるなら、まずは香り雑貨やナチュラルフレグランスから始めるのがベストです。BLACKLETTERSのように、上質な精油を使ったプロダクトを活用して、自然とともにある豊かな時間をぜひ体験してください。




