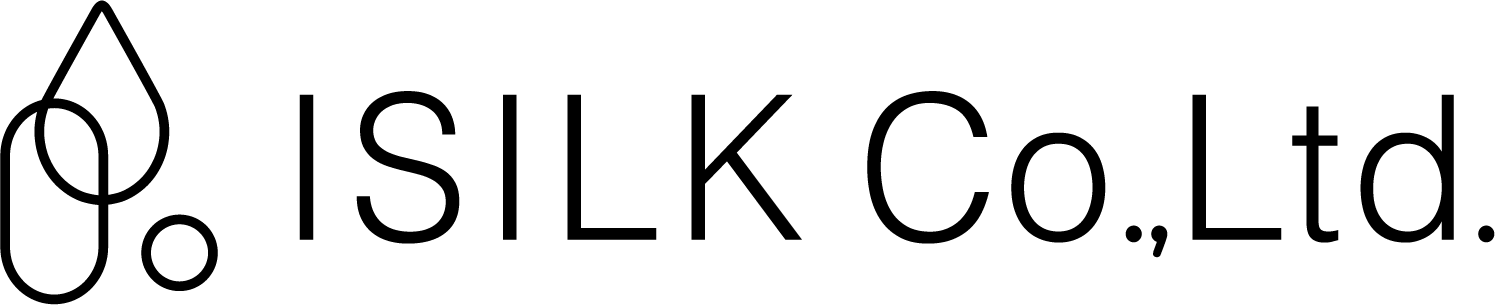香りとキャンドルの相性とは?ソイ・蜜蝋・パームワックスの違いと精油の使い方ガイド
はじめに|香りを“灯す”という発想
キャンドルやお香など、香りの演出方法に関心が集まる中、「香りを焚く」のではなく「暮らしの中でどう灯すか」という視点が注目されています。
とくに日本の自然から生まれた香木・黒文字(クロモジ)といった素材は、精油だけでなく“キャンドルの芯”やワックスとの相性も含めて、香りの新しい可能性を秘めています。
本記事では、キャンドルと香りの関係性、天然ワックスの違い、黒文字の再活用アイデアまで詳しく解説します。
キャンドルに香りを加えるときの注意点
キャンドルに精油や香料を加えると、アロマ体験としては魅力的ですが、実は以下のような課題があります。
-
高温で香り成分が変質・劣化する
-
ススや煙が出やすくなる
-
香料によって燃焼が不安定になる
そのため、香りと火を“共存”させるには、適したワックス選びと緻密な処方設計が必要です。
また、天然精油の中には燃焼時に刺激を伴うものもあるため、用途に応じて「香るための成分」と「燃やすことに適した成分」を見極める視点も大切です。
天然系キャンドルワックス3種の比較
ソイワックス(大豆由来)
-
融点:47〜57℃
-
特徴: 煤が出にくく空気を清浄。長時間燃焼&香りが広がりやすい
-
向いている香り: 柑橘・ハーブ系
-
持続性: ゆっくり溶けるため香りがなじみやすい
ミツロウ(蜜蝋)
-
融点:62〜65℃
-
特徴: 自然由来。独特の甘い香りがあり、消火時もにおいが残りにくい
-
注意点: カビが生えやすいため防腐対策が必要
-
利点: 火を灯さなくてもやさしく香る“素焼きタイプ”にも活用可能
パームワックス(ヤシ由来)
-
融点:約57℃
-
特徴: 結晶模様が美しくインテリア性◎。炎が安定して燃焼
-
環境配慮: RSPO認証など、持続可能なパーム油を選ぶことが重要
- テクスチャ: 結晶構造が硬く、型取りの自由度も高い

木芯(ウッドウィック)と黒文字の可能性
キャンドルの芯にはコットンのほか、“木芯”という選択肢も。焚き火のようにパチパチと音を立てながら燃えるため、視覚・聴覚も楽しめる演出ができます。
ここで注目されるのが、日本の森で採れるクロモジ(黒文字)。
-
精油として抽出された後の枝葉は、従来廃材として扱われてきた
-
粉砕・圧縮して木芯として再活用すれば、焚くたびにほのかに香るキャンドルに
🔥 黒文字の木芯が実現すれば、五感すべてで楽しめる唯一無二のキャンドルが生まれるかもしれません。

精油をキャンドルに使う際のポイント
天然精油をワックスに加える場合、以下の点に注意しましょう。
-
加えるタイミング: ワックスが少し冷めてから(約60℃前後)
-
配合量の目安: 全体の3〜6%程度
-
安定性の確認: 香りが飛びすぎないか、ススが出ないか試作検証が必要
-
アレルゲン・皮膚刺激成分: 安全性データを必ず確認
-
ブレンド例:
-
リラックス系:クロモジ+ラベンダー
-
シャープ系:ユーカリ+ティーツリー
-
温感系:シナモン+オレンジスイート
-
BLACKLETTERSの挑戦|“灯す香り”を秩父から
私たちが展開するナチュラルフレグランスブランド【BLACKLETTERS】では、秩父のクロモジ精油を使った香水・ディフューザーを展開しています。
さらに今後は、クロモジの枝を芯やキャンドル素材として活かす開発も進行中。
-
森の香りを“嗅ぐ”から“灯す”へ
-
香りと素材の産地がつながる体験を創出
-
森林資源を余すことなく使い、循環型の製品設計へ
-
秩父の森と都市の暮らしを結ぶ、香りの新しいかたちを提案
まとめ|香りとキャンドルの“調和”を楽しもう
キャンドルに香りを加えるには、燃焼や安全性への配慮が欠かせませんが、工夫次第で「空間ごと記憶に残る香り体験」が実現できます。
特に、自然素材との相性や精油のブレンドを丁寧に選ぶことで、心を癒す灯りが日々の暮らしにやさしく寄り添います。
🌿 秩父の森から生まれた黒文字の可能性を、キャンドルにのせて灯してみませんか?