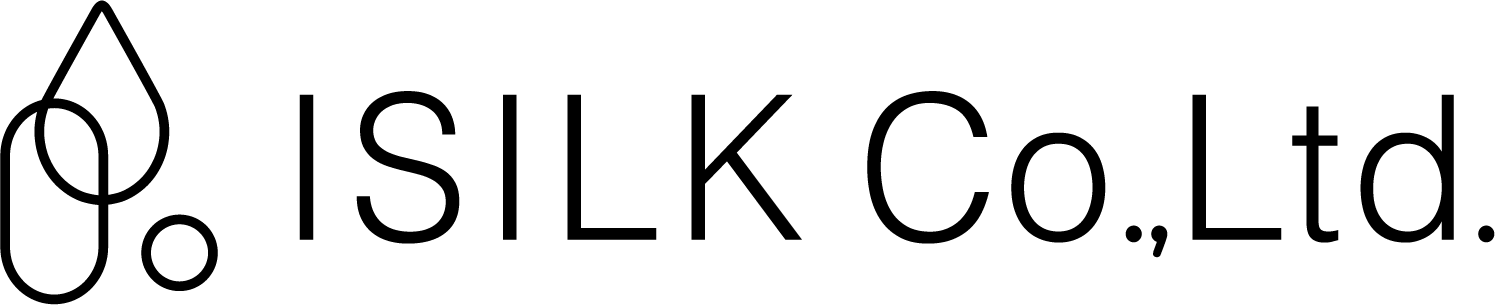黒文字の香りと楽しむクラフトコーラ|歴史・作り方・“香る”クラフト精神
クラフトコーラとは?自然派志向が生んだ“飲む香り”
「クラフトコーラ」とは、大手メーカーが製造する既製品とは異なり、ハーブやスパイス、柑橘類などの天然素材を使い、手作りされる個性派コーラのこと。
近年では健康志向やサステナビリティへの関心の高まりとともに、日本全国で独自レシピのクラフトコーラが誕生しています。
その中でも特に注目されているのが、日本固有の香木「黒文字(クロモジ)」を使ったクラフトコーラ。自然な香りと爽やかさ、奥深さを兼ね備えた“香るコーラ”として支持を集めています。

コカ・コーラの起源と“クラフト”の対比
1886年、アメリカ・ジョージア州で薬剤師ジョン・ペンバートンによって発明されたのが、現代のコーラの原型です。もともとは神経疲労や頭痛に効く「薬用シロップ」として開発され、当時のレシピにはコカの葉、ワイン、さまざまなスパイスが使われていました。
その後、禁酒法の影響でアルコールを排除し、ソーダ水で割ったことで今の「炭酸コーラ」が誕生。ブランド戦略と大量生産により世界中に広まったコカ・コーラは、均質で記憶に残る“味と香り”を作り上げました。
一方で、クラフトコーラはその真逆。手作業による小ロット生産、地元食材の活用、香りの個性を大切にする“クラフト精神”が核にあります。

クラフトコーラのレシピと体験:黒文字を使ってみた
▶ 使用材料(シロップ約500ml)
-
水…400ml
-
三温糖…400g(上白糖でも可)
-
クローブ(ホール)…40粒
-
カルダモン(ホール)…20粒
-
シナモンスティック…3本
-
バニラビーンズ…1/2本(またはバニラエッセンス)
-
レモン(ノンワックス)…2個
-
黒文字の枝…2〜3本
▶ 作り方と香りの変化
-
水と砂糖を鍋で加熱し、香辛料をすべて投入。
-
レモンの皮と果汁を加え、黒文字の枝も一緒に煮出す。
-
弱火で30分煮込み、シロップ状になったら漉して完成。
完成したクラフトコーラは、黒文字の清らかなウッディシトラスの香りが中心に据えられ、カルダモンやクローブの刺激が全体を引き締めます。
甘さの中に自然の複雑さと透明感がある、まさに“飲む香り”という表現がぴったりの味わいです。

黒文字とは?日本の森が育む香りの植物
黒文字(クロモジ)は、クスノキ科の落葉低木で、日本の山地に広く自生しています。爪楊枝や漢方薬の素材としても古くから使われており、特にその精油は「和製ローズウッド」とも称される高級な香り。
-
爽やかなシトラス感とウッディ感
-
抗菌・リラックス・整肌作用
-
飲用・アロマ・コスメなど用途が広い
クラフトコーラでは、煮出すことで香りが湯気に乗って立ち上がり、口に含むとほんのり甘さと苦味が広がります。

ISILKの想い:香るクラフト×飲むクラフト
私たちISILKでは、秩父の自然素材を活かし、クラフトフレグランスブランド「BLACKLETTERS(ブラックレターズ)」を展開しています。
その中核を担う香り素材が、この黒文字精油。
-
▶ 香水・キャンドル・アロマに使える香り
-
▶ 原材料は秩父産の間伐材や野生黒文字
-
▶ 地域の森を守りながら製造
クラフトコーラで「飲む香り」を、香水で「纏う香り」を。黒文字という一つの素材が、二つの体験をつなげています。
クラフトとは、手間と物語のあるもの
クラフトコーラを作ってみて気づいたのは、「手間ひまのかかる味には、物語がある」ということ。材料を選び、煮出して、香りを感じながら味を整える——。その時間すべてが、私たちにとって癒しの体験でした。
そして、香りとは単なる嗜好品ではなく、「心と記憶をつなぐもの」。クラフトコーラの流行は、私たちが日常に小さな喜びや自然とのつながりを求めている証なのかもしれません。

まとめ:クラフトの香りとともに、豊かな暮らしを
黒文字を使ったクラフトコーラは、ただの飲み物ではなく、自然・香り・文化が融合した“体験”です。
香水でもコーラでも、「黒文字の香り」は私たちの暮らしにやさしさと余白を与えてくれます。
ぜひ、BLACKLETTERSの世界観や香りのラインナップも覗いてみてください。あなたの五感が喜ぶ、新しい発見がきっとあるはずです。
▶ ISILKの商品一覧はこちら:https://isilk.jp
👉 黒文字の香りをもっと知る ― BLACKLETTERS 公式ページへ